就職支援には、さまざまな状況に応じて利用できる公的支援制度やサービスがあります。このページでは、働き世代や小児がん経験者、ひとり親家庭、障害のある方に向けて、就職支援の内容や方法を分かりやすく紹介します。
働き世代のための就職支援
長期療養者就職支援事業
がんにより長期の療養(経過観察・定期的な通院など)が必要な方が、安心して就職活動を行えるよう支援するため、ハローワークでは専門の相談員を配置しています。
療養と両立可能な働き方や職場環境に関する情報提供、履歴書や面接への対応方法、キャリアプランの相談など、就職活動に向けたさまざまなサポートを行っています。また、がん相談支援センターと連携し、患者さんの同意のもとで治療状況や経過、就労時に配慮が必要な点などの情報を共有し、一人ひとりの希望や状況に応じた職業相談や職業紹介を行っています。
がん相談支援センターが設置されているがん診療連携拠点病院などでは、院内での就労相談や情報提供を実施している場合もあります。主治医や医療ソーシャルワーカーと連携しながら、治療と就労の両立を目指す体制が整えられつつあります。
● ハローワークによる支援
ハローワーク飯田橋では、長期療養者(がん患者等)の方を対象とした専門の就労支援を実施しています。
個々の体調や通院状況に配慮した働き方の相談、応募書類の作成支援、面接に関するアドバイスなど、個別の状況に応じたきめ細かなサポートが特徴です。
● 若年層向け支援:若者サポートステーション
若年層(概ね15歳~49歳)で、がんなどにより長期療養を経験した方への就労支援も進められています。全国の若者サポートステーションでは、専門的な支援体制が整っています。
ハローワークインターネットサービスで全国のハローワークの所在地が検索できます。
- やまがたがんサポートハンドブック(山形県)
- 厚生労働省HP 長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065173.html
- 地域若者サポートステーションHP:全国のサポステhttps://saposute-net.mhlw.go.jp/station_detail/sec0418-hokusei.html
- エーザイ株式会社運営サイト・レディルナガーデンがんの療養を続けながらの就業をハローワークが支援~長期療養者等就職支援モデル事業~https://brecaregarden.jp/support/work_support.html
職業訓練支援
● 教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は、厚生労働省が実施する雇用保険の給付制度で、対象の講座を修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
教育訓練給付制度には、そのレベルなどに応じて、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
がん治療後に再就職や転職、キャリアチェンジを目指す方、働きながらスキルアップしたい方にとって、経済的な負担を軽減できる心強い制度です。詳細については以下の厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」をご覧ください。
● 求職者支援制度
「求職者支援制度」は、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練を通じてスキルを身につけ、早期の就職を目指すための支援制度です。これは、ハローワークからの支援指示に基づいて職業訓練を受講する際、生活支援として毎月10万円の給付金が支給される制度です。本人の収入が月8万円以下であることなどが条件です。
この制度は特に、治療を終えたばかりで就労に不安を感じている方や、新たな働き方を模索している方にも活用していただけます。
● 職業能力開発促進センター
全国各地に「職業能力開発促進センター(通称:ポリテクセンター)」があります。これらは、国(厚生労働省所管の独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)が運営しており、求職者や離職者、キャリアチェンジを考える方に向けて職業訓練を提供しています。
● 地方自治体が運営する職業能力開発センター
ポリテクセンター以外にも東京都と埼玉県の自治体が運営する職業訓練施設があります。地域の雇用ニーズに合った実践的な訓練が受けられます。
【東京都】
【埼玉県】
- 山口県がん患者サポートブック がんと仕事とお金 第3版
- 厚生労働省HP:求職者制度のご案内https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
- 厚生労働省HP:就職支援・給付金などについて知る https://www.mhlw.go.jp/helotraining/support/
小児がん経験者のための就職支援
公的機関による相談支援
小児がんを経験した方の就労については、小児がん拠点病院やがん相談支援センター、長期フォローアップ外来、ハローワークで相談することができます。
● 小児がん拠点病院
小児がん拠点病院においてはAYA世代に対し、就学・就労等について個々の状況に応じた支援を行います。
AYA世代においては、年代によって、就学、就労等の状況や心理社会的状況が様々であることから、個々の状況に応じ、多様なニーズを踏まえた、全人的ながん医療及びライフステージに応じた支援を提供すること。
「小児がん拠点病院等の整備について」(厚生労働省 健発0801第17号 令和4年8月1日)より引用
● がん相談支援センター
がん相談支援センターにおいても同様に、他の行政機関や医療機関等と連携し、就学・就労等の相談支援を行います。

● 長期フォローアップ外来
小児がんの治療を終えた後も、晩期合併症の予防や生活支援を目的として設けられた外来です。就学や就職、結婚など、ライフステージの変化に伴う心配ごとについて医師や看護師に相談することができます。移植後フォローアップ(LTFU)外来では、リーフレット※による案内があります。
※ 移植後就労支援リーフレット③移植後 (外部リンク)
● ハローワーク
ハローワークでは、「長期療養者就職支援事業」の一環として、小児がん経験者に対する就労支援を行っています。専門の相談員がハローワークに配置されており、がん相談支援センターと連携しながら、患者さんの同意のもとで治療状況や経過、就労時に配慮が必要な点などの情報を共有し、一人ひとりの希望や状況に応じた職業相談や職業紹介を行っています。
また、がん相談支援センターが設置されているがん診療連携拠点病院などでは、ハローワークによる院内での出張相談も実施されています。
ハローワークインターネットサービスで全国のハローワークの所在地が検索できます。
● 若年層向け支援:若者サポートステーション
若年層(概ね15歳~49歳)で、がんなどにより長期療養を経験した方への就労支援も進められています。全国の若者サポートステーションでは、専門的な支援体制が整っています。
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
悪性新生物(がん)などの慢性疾患を抱える子どもたちが、将来にわたって自立した生活を送ることができるよう、医療・教育・社会面で包括的な支援を行う制度です。主に、日常生活や学校生活における療育に関する相談が可能で、将来の就労を見据えた支援やフォローアップについては、自立支援員が継続的に伴走します。
都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市で実施しています。相談窓口は、小児慢性特定疾病児童等自立支援センターのホームページから検索できます。
民間団体による支援
認定NPO法人ハートリンクワーキングプロジェクト(新潟県新潟市)
小児がん経験者職業訓練施設「ハートリンク喫茶」において就労支援活動しています。
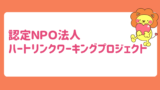
小児・AYAがん経験者のための就活講座 (ノバルティスファーマ株式会社)
がん経験者の就職活動に必要な知識や心構えについて、専門家の講義とがん経験者の体験インタビューを動画配信しています。

- がん情報サービス:小児がんの相談・病院 https://ganjoho.jp/public/life_stage/child/reference.html
- 小児がん拠点病院等の整備について(健発0801第17号令和4年8月1日)000972172.pdf
- 小児がんの就労について 0000045696.pdf
- 厚生労働省HP 長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065173.html
- 厚生労働省HP 小児慢性特定疾病対策の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973.html
- アフラックHP:がんの保険がよくわかるサイト 小児がん経験者の就労。その人自身の魅力を知ってもらって、就労に繋げたいhttps://www.aflac.co.jp/gan/yokuwakaru/article/page52.html
ひとり親家庭のための就職支援
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親)
母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援を図るため、全国各地に母子家庭等就業・自立支援センターが設置されえています。就業相談をはじめ、就業支援講習会、就業情報の提供などの就業支援サービスの他にも、法律、養育費相談などの生活支援サービスなど様々な支援が利用できます。
相談窓口
母子寡婦福祉連合会
- 厚生労働省HP:母子家庭等就業・自立支援センター事業についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062967.html
- 神奈川県母子家庭等就業・自立支援センターHP:https://www.khitorioya.com/
- 堺市HP:母子家庭等就業・自立支援センターhttps://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/sodan/boshi/jiritsushien.html
- 八王子市子育て応援サイトHP:母子家庭等就業・自立支援センター事業とはhttps://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/mokuteki/hitorioyakatei/shugyoshien/792.html
高等技能訓練促進費等(ひとり親)
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度で、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業とは異なる制度です.修業期間の全期間(上限4年)について毎月100,000円 (市町村民税非課税世帯)又は月額70,500円(市町村民税課税世帯)が支給されます。
また、高等職業訓練修了支援給付金は、高等職業訓練校を修了した方に対して50,000円が支給されます。
相談窓口
各自治体担当課(こども家庭部こども福祉課)
- 厚生労働省HP:高等職業訓練促進給付金のご案内https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062967_00005.html
自立支援教育訓練給付金(ひとり親)
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養している方が、就職や収入の安定につながる教育訓練(資格取得講座など)を受講する際に、受講費用の一部が支給される制度です。
この制度は、「母子家庭の母」「父子家庭の父」が対象で、指定された講座を受講した場合に受講料の60%(最大上限あり)が支給されます。
相談窓口
各自治体担当課(こども家庭部こども福祉課)
- 厚生労働省HP:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
この制度は、ひとり親家庭の親またはその子どもが「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)」に合格し、就労や進学など自立に向けた一歩を踏み出すための支援制度です。学び直しを希望する方や、高校を中退された方などが対象となり、受験に必要な講座の受講料などが支援されます。
■ 支援の内容
- 高卒認定試験に向けた通信・通学講座の受講料の一部を助成します。
- 受講修了後、一定の要件を満たせば合格報奨金の支給もあります。
※支援の内容や金額、対象となる講座は自治体によって異なります。
■ 対象となる方
- ひとり親家庭の親
- ひとり親家庭で育つ児童(おおむね20歳未満)
- 母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けていること。
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められること。
※ 自治体によって、児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること等がありますので、お住まいの自治体ホームページや窓口でご確認ください。
- こども家庭庁HP:高等学校卒業程度認定試験合格支援事業について https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/goukakushien
- 東京都福祉局HP:ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hitorioya_shien/syurou/kousotu.html
ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業
この事業では、専門の支援員(母子・父子自立支援プログラム策定員)が、面接や相談を通してご本人の希望・経験・生活状況を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った「自立支援プログラム(個別支援計画)」を策定します。
その上で、ハローワーク(公共職業安定所)との連携や、「生活保護受給者等就労自立促進事業」などの各種制度を活用しながら、就職・転職、資格取得、職業訓練への参加などに向けた具体的なサポートを行います。
■ 対象となる方
- 児童扶養手当を受給している方
- 児童扶養手当の受給見込みがある方(例:配偶者等からの被害により離別など)
- 同様の所得水準にあるひとり親家庭の方
- ※生活保護を受給している方は対象外となる場合があります(自治体によって異なります)
■ 主な支援内容
◎ 個別支援プログラムの策定
- 面接を通して生活状況や就労への希望・課題を整理
- 資格取得・職業訓練・転職など、目標に合わせた支援計画を作成
◎ ハローワークとの連携
- ハローワークの「就労支援ナビゲーター」との協働による職業相談・紹介
- ハローワーク訪問の同行支援
- 地域就労支援拠点との連携(例:就労支援コーナー)
◎ 就労に向けた具体的支援
- 履歴書・職務経歴書の作成支援
- 面接対策や応募企業選びのアドバイス
- 就職活動中の不安や生活上の悩みへの相談対応
◎ 関係機関との連携支援
- 必要に応じて、健康支援センターや児童相談所、母子生活支援施設の利用も案内している自治体もあります。
- こども家庭庁HP:母子・父子自立支援プログラム策定事業について https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/goukakushien
- 東京都福祉局HP:母子・父子自立支援プログラム策定事業 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hitorioya_shien/syurou/puroguram.html
- 練馬区ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業 https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/syuurou.html
障害のある方のための就職支援
ハロートレーニング(障碍者職業訓練)
ハロートレーニングは、就職や再就職に向けた職業スキルの習得や社会復帰のための支援制度です。全国のハローワークや委託訓練機関で実施されており、ITや介護、事務など幅広い分野の訓練があります。
がんの治療による心身的変化から、「これまでと同じ働き方が難しい」と感じる方も少なくありません。ハロートレーニングでは、自分のペースで学び直し、新たな仕事への準備を整えることができます。
● 国立職業リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)
国立職業リハビリテーションセンターは、障害のある方への職業適性等の理解・把握のための職業評価、就職に必要な技能・知識等を習得するための職業訓練、就職に必要な情報を提供しています。中央広域障害者職業センターと中央障害者職業能力開発校から構成され、障害のある方に対して一貫した職業リハビリテーションを実施しています。施設内には、就労するための訓練施設や、職場復帰を支援するための相談窓口などがあります。
● 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県加賀郡吉備中央町)
障害のある方々の職業的自立と社会参加を支援するための総合的な職業リハビリテーション施設です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が運営し、医療・福祉・教育・職業訓練が一体となった支援体制を提供しています。
センターでは、障害の特性や個々のニーズに応じた多彩な訓練コースを提供しています。訓練生の生活を支えるため、宿舎棟や厚生棟などの施設も整備されています。
● 障害者職業能力開発校
障害者職業能力開発校も同じく身体障害、精神障害、発達障害、難病など、さまざまな障害を持つ方々を対象に、就職に必要な技能や知識を習得するための職業訓練を行う公的な教育機関です。
全国に17か所(北海道、青森県、宮城県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県(神戸市、伊丹市)、広島県、福岡県、鹿児島県)設置されています。
相談窓口
お住まいの近くのハローワーク
ハローワークインターネットサービスで全国のハローワークの所在地が検索できます。
- 厚生労働省HP:ハロートレーニング(障害者訓練)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shougaisha.html

